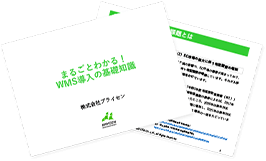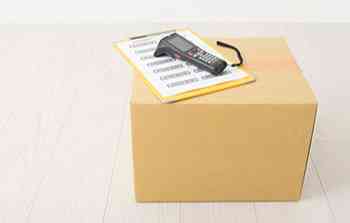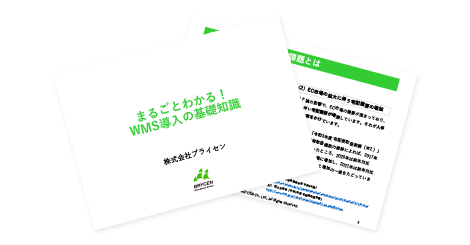基幹システムとは?
基幹システムとは、企業や組織の主要な業務プロセスを支えるための重要な情報システムを指します。具体的には、財務、人事、製造、販売、物流などの機能が含まれ、通常は統合されたソフトウェアやデータベースを使用して運用されます。
基幹システムの主な目的は、業務の効率化、データの一元管理、意思決定の支援などです。多くの場合、ERP(Enterprise Resource Planning)システムとして知られるソフトウェアが用いられ、部門間の情報共有を円滑にし、業務の透明性を高める役割を果たします。
このようなシステムは、企業の競争力を向上させるために不可欠であり、長期的な成長を支える基盤となります。
ここで余談とはなりますが先日行われた国際物流総合展2024で弊社のブースにご来場頂いたうちの約2~3割の方が導入している基幹システムの切り替えに伴い、物流部門のみ切り離したいという要望がございました。これは今まで基幹システムをカスタマイズして物流(倉庫)管理をおこなってきたものの現場の方からの意見や要望を実現させると莫大な金額がかかることや基幹システムをこれ以上カスタマイズ出来ないという事情があるようです。
基幹システムは前述した通りで企業や組織の主要な業務プロセスを支えるためのシステムとありますが、物流(倉庫)現場では機能不足が否めず、痒いところに手が届かないという意見をよく耳にします。こういった背景があり、基幹システムの切り替えのタイミングでWMS(倉庫管理システム)の導入が検討されているようです。
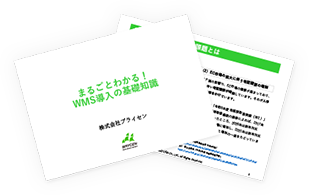
基幹システム(ERPなど)とWMS(倉庫管理システム)を連携するメリットとデメリット
先ほど、基幹システムとWMS(倉庫管理システム)を切り離すとお伝えしましたが切り離してそのままにしておくわけにはいかないので連携するメリットやデメリットについてお伝えします。
メリット
在庫管理の効率化と正確性向上
ERPとWMSを連携させる最大のメリットは、在庫管理の効率化です。
ERPは理論在庫(発注・入出荷を基にした予測在庫)を管理し、WMSは実在庫(倉庫内の実際の在庫)をリアルタイムで追跡します。WMSの入出荷データをERPに連携することで、理論在庫と実在庫の乖離を最小限に抑え、全社で正確な在庫情報を共有可能です。
例えば、EC事業者が在庫切れによる販売機会損失を防ぎ、過剰在庫による保管コストや廃棄リスクを回避できます。棚卸作業も効率化され、作業時間は従来の半分以下に短縮される場合も。人的ミスの削減により、誤出荷やデータ入力エラーが減り、信頼性の高い在庫管理が実現します。
WMSのリアルタイムデータは、購買や販売部門とも連携し、需要予測の精度を高め、物流全体の最適化を支えます。
業務プロセスの自動化と効率化
ERPとWMSの連携により、受注から出荷までのプロセスが自動化され、業務効率が飛躍的に向上します。ERPで処理された受注情報がWMSに即座に連携され、ピッキングや出荷指示が自動生成。手作業による遅延やエラーを大幅に削減します。
例えば、ECサイトからの大量注文をWMSがリアルタイムで受け取り、最適なピッキングルートを提案し、作業時間を短縮。WMSの在庫アラート機能は、在庫不足を未然に防ぎ、発注タイミングを最適化します。返品処理も迅速化され、顧客対応のスピードが向上。トレーサビリティの強化により、商品の追跡も容易に。コロナ禍でのEC需要急増や人材不足の中、少ない人員で大量の出荷を処理可能に。
業務プロセスの自動化は、物流現場の生産性を高め、コスト削減と顧客満足度の向上を両立します。
データの一元化による意思決定の迅速化
ERPとWMSの連携は、倉庫データ(在庫状況、入出荷履歴)と経営データ(売上、財務)を一元化し、リアルタイムで可視化します。経営陣は正確なデータを基に、戦略的な意思決定を迅速に行えます。
例えば、在庫回転率を分析し、売れ筋商品の在庫を最適化することで、販売機会を最大化。物流コストの分析で、輸送や保管の無駄を削減し、利益率を向上させます。複数拠点を持つ企業では、WMSで各倉庫の在庫を一括管理し、ERPで全体の経営状況を把握。サプライチェーン全体の効率化が図れます。リアルタイムデータは、顧客からの問い合わせにも即座に対応でき、満足度向上に貢献。
データの一元化は、市場変化に柔軟に対応する基盤となり、競争力強化や売上拡大を支える重要な要素です。
デメリット
高い初期導入コスト
ERPとWMSの連携には、システム開発、API設定、インフラ構築が必要で、初期コストが高額になる場合があります。
例えば、ソフトウェアライセンス費用(100万円~500万円)、カスタマイズ費用(50万円~300万円)、サーバーやネットワークのインフラコスト(50万円~200万円)が発生。
オンプレミス型の場合、初期投資が1,000万円を超えることも珍しくありません。クラウド型でも、月額費用や統合コストがかかります。さらに、従業員向けトレーニング費用(10万円~50万円)や、データ移行のためのコンサルティング費用(50万円~200万円)も必要に。
中小企業では予算の負担が大きく、費用対効果を慎重に評価する必要があります。コストに見合う成果(在庫削減や効率化)を出すには、事前のシミュレーションと長期計画が不可欠です。
導入期間の長期化と現場の混乱リスク
システム連携には、データの整合性確保のためのカスタマイズやテストが必要で、導入期間が数か月から1年以上に及ぶ場合があります。
例えば、ERPとWMSのデータフォーマットを調整し、連携テストで不具合を解消する作業に時間を要します。この間、既存システムとの並行運用が必要で、従業員の操作ミスやデータ不整合により、現場で混乱が生じるリスクも。複数ベンダーが関与する場合、仕様の調整やコミュニケーションの複雑さから、プロジェクト遅延の可能性が高まります。
現場スタッフの適応にも時間がかかり、生産性が一時的に低下する場合も。混乱を最小限に抑えるには、段階的な導入計画や十分なトレーニング、ベンダーのサポートが重要。導入期間の長期化は、業務への影響を慎重に管理する必要があります。
カスタマイズと相互運用性の課題
ERPとWMSが異なるベンダーから提供されている場合、相互運用性が不足し、カスタマイズが必要になります。
例えば、API連携でデータフォーマットの違いや不具合が発生し、追加開発(50万円~200万円)が必要なケースも。
古いERPやWMSの場合、最新システムとの互換性が低く、アップグレードや再構築(100万円~500万円)が求められることもあるでしょう。
くわえてカスタマイズは、長期的なメンテナンスコスト(年間50万円~150万円)にも影響し、システム更新のたびに追加費用が発生します。
相互運用性の課題は、データ同期の遅延やエラーを引き起こし、業務効率を損なうリスクも。
解決には、ベンダーの技術力や過去の連携実績を確認し、標準化されたAPIや柔軟なシステムを選ぶことが重要。カスタマイズの負担を軽減し、安定運用を目指す必要があります。
ERPとWMS連携の比較表
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 在庫管理 | 理論在庫と実在庫のリアルタイム同期、棚卸時間削減 | データ整合性のための初期設定が必要 |
| 業務効率 | 受注から出荷の自動化、ピッキング・返品処理の最適化 | 導入中の現場混乱リスク |
| データ活用 | 全社データ一元化、意思決定の迅速化 | 相互運用性の課題、カスタマイズ費用 |
| コスト | 長期的な効率化でコスト削減 | 初期導入コスト高(100万円~1,000万円以上) |
| 導入期間 | 長期的な生産性向上 | 導入に数か月~1年以上、テスト複雑 |
まとめ
基幹システムとWMSの連携は、企業の物流および在庫管理において多くのメリットをもたらします。これにより、データの継続性と正確性が向上し、業務の自動化や効率化が進むため、リードタイムの短縮また、顧客満足度の向上やヒューマンエラーの削減といった効果も期待され、全体的な業務フローの迅速化とスムーズな意思決定をサポートします。
一方でセキュリティ、初期導入コストやシステム連携中に伴うカスタマイズの難しさ、運用面でのコスト増加やシステム障害時のリスクといった対処も存在します。
基幹システムとWMSの連携を成功させるためには、これらの利点と戦略を十分に検討する必要があります。計画通りに導入・運用されれば、業務の効率化とコスト削減、そして競争力の強化を実現することは間違いないでしょう。ブライセンのクラウド型倉庫管理システムCOOOLaは多様な機能と柔軟なカスタマイズを強みとしているシステムです。直近でもパッケージの基幹システムや自社向けの基幹システムとの連携実績もございます。基幹システムから物流部門を切り離す為にWMSの導入を検討している、基幹システムとWMSを連携させたいなどお考えでしたら右上にあるお問い合わせフォームから是非ご連絡いただければと思います。